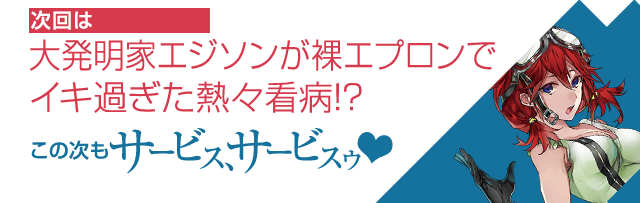時震の影響でおかしくなった歴史を修正する。
それが僕たち航時局歴史管理課、通称THRのお仕事。
とはいえこのところはさしたる時震もなく、エージェントの面々は毎日暇を持て余している。おしゃべりしたり食事をしたり趣味に興じたりと、思い思いに時間を潰しているようだった。
「いよっしゃあああああ! 二十一人抜きぃっ!」
古代中国で三国一と謳われた武将、呂布(りょふ)奉先(ほうせん)もまた、アーケードゲームで余暇を満喫していた。その溢れんばかりの闘争本能を、格闘ゲームで発散していたのだ。
複合デパートの地下フロア――。ここが現代における彼女の戦場なのである。
「格上スコアの相手にあけぼのフィニッシュ決めるのは、最高に気分がいいな」
筐体の前で、奉先がにこりと微笑む。
長いツインテールは彼女のトレードマーク。豊満なバストとすらりと長い足が魅力的な、THRきってのセクシー系美少女だ。胸の谷間と太ももが強調されたチャイナ風改造制服は、いつ見ても「エロ過ぎ」の一言である。
だが、現在彼女が周囲の注目を集めているのは、その容姿だけが理由ではないようで。
「おい、今の反応見たかよ?」「小足見てから昇竜余裕で決めやがった」
「やっぱ上位ランカーは違うな」「この店じゃもう、奉先さんのスコア抜けるヤツいねーだろ」
「あんな可愛いのにゲーム強いって、ほんとすげーよな」
ゲーマーのお兄さんたちが、奉先の背後で腕組みをしながら囁き合っている。彼らはいわゆる〝ベガ立ち勢〟だが、今日の僕はそんなベガさんたちのひとりだった。
奉先に「ゲーセン行こうぜ」と誘われてなんとなく付いてきてみた結果、こうして彼女のスーパープレイを拝むことになったのである。
もともと奉先が格ゲー好きなのは知っていたが、まさかゲーセンでも無双伝説を作り上げていたとは……。どこのプロゲーマーだよ。
観客のひとり、ニット帽を被ったお兄さんが「なあなあ」と声をかけてきた。
「おたく、奉先さんの友達?」
「ええまあ」
「あの子って何者なの? モデルかなんか? それにしては格ゲー上手すぎだけど」
「公務員ですよ。本業は武将ですけど」
彼は「武将?」と首を傾げていたが、それ以上の説明は面倒くさいのでやめておいた。
「というか逆に聞きたいんですけど、奉先ってそんなすごいプレイヤーなんですか?」
「そりゃあもう」ニット帽さんが深く頷いた。「ここらの店じゃ負け知らずの格ゲーマーだよ。〝グラップ潰しの奉先さん〟つったら、その手の掲示板で専用スレが立つほど有名なんだけど……。おたく、知らなかった?」
ビックリ。まったく知らなかった。
彼がスマホで見せてくれたネット掲示板の画面には、確かに奉先について言及されているスレッドがいくつも乱立していた。彼女の画像付きで。
ルックスからして目立つからなあ、この武将娘は。
「奉先さん、格ゲーの対人スコアもハンパないけど、ナンパ男の撃墜数もものすごいらしいよ。どんなイケメンに声をかけられようと『あたしにはご主人様がいるから』ってすげなく一蹴しちゃうんだと」
「格ゲーでもナンパでも、絶対相手につかませないようとしないからな。色んな意味で〝つかみ(グラップ)潰し〟なんだとか」
冗談めかして言うお兄さんたちにつられて、ついつい笑ってしまう。なんだその通り名。
「ともあれ、ゲーセンの奉先は無敵ってわけですね」
現代に来て一年ちょっとのくせに、いつの間にこんな有名プレイヤーになっていたのやら。
これもやはり武将としての才能、〝武力〟の賜物だろうか。常人離れした反射神経や動体視力、そして卓越した勝負勘が、奉先を無敵のゲーマーたらしめているのかもしれない。
「まさに才能の無駄遣い……」
僕がため息をついていると、筐体に向かっていた奉先がこちらを振り向いた。
「なあ。次、誰かワンラウンド勝負しねえ?」
「え。奉先さんとですか?」お兄さんのひとりが尋ねる。
「そりゃそうだろ。あたしはひとりでオンライン対戦やってるより、面と向かってやるバトルの方が好きなんだ」
しかし、お兄さんたちは揃って「遠慮するっす」と苦笑い。
まあ当然だろう。彼らは奉先の実力を知っているからこそ、背後で観客に甘んじていたのだ。勝てるつもりなら最初からベガ立ちはしない。
「なんだよもう。揃いも揃ってチキンじゃねーか」奉先がこちらに目を向けた。「そんで、隊長さんはどーすんだ? あたしと対戦しねえのか」
「え? 僕?」
「隊長さんなら、勝負からは逃げねえだろ。毎日のようにフレドリカさんに当たって砕けろを実践してるもんな。玉砕ばっかだけど」
鼻を鳴らす奉先に、僕はむっとしてしまう。
「玉砕ばっかで何が悪いの。失敗は成功の母だってアルちゃんも言ってるじゃない」
「どうかなあ。成功するかなあ。ここであたしの挑戦を無視するようなチキンじゃ、むしろ見捨てられちゃうんじゃねえかなあ」
ううむ。ドMのくせに生意気な。有名プレイヤーとしてちやほやされてるからって、ちょっと調子に乗りすぎではないだろうか。
ここはTHR隊長として、彼女にきっちりお仕置きをしてやる必要があるだろう。
僕はまっすぐ奉先を睨みつけ、
「よしわかった。勝負に乗るよ」
「さすが隊長さん。そう言ってくれると思ってたぜ」
「ついでに、こういうのはどうかな。勝ったら、負けた方の言う事をなんでもひとつ聞く」
「燃える提案してくれるじゃねーか。いいぜ。受けて立つ」奉先が白い歯を見せて笑う。
勝負好きな彼女のことだ。レートを上げれば必ず食いついてくると思っていた。
「でも隊長さん、ホントにあたしに勝てる気でいるのかよ。そんなにこのゲーム得意だっけ?」
「いや。そもそも格ゲーで勝負するとはひとことも言ってないし」
奉先が「え?」と首を傾げた。
数分後、僕たちは暗がりの中でぴったり身を寄せ合っていた。
二人掛けのボックス型ゲーム筐体の中だ。幅一メートル強くらいの狭い座席に、奉先と並んで座っている。お互いの体温が感じられるくらいの距離感だ。
顔には揃って3Dメガネ。手には銃座型のコントローラー。僕たちはいわゆる、体感型ガンシューティングゲームに挑戦しようとしているわけである。
「まさか隊長さん、こういうゲームで挑んでくるとはな……」
「正々堂々の勝負が好きな奉先なら、お互いフェアに競えるゲームの方がいいでしょ」
「そりゃあそうだけどさあ」
なにやら奉先、浮かない表情である。真正面、デモ画面の中で牙を剥くゾンビたちのCGモデルを見つめ、顔を引き攣らせてしまっていた。
「なんで敵がゾンビなんだよ……。キモすぎるだろ……」
「もしかして奉先って、こういうの苦手?」
「べ、別にんなことねえよ? 死体なんざ戦場で見慣れてるしな」
そういう奉先の声は、やや上ずっているようにも聞こえる。
もともと僕は知っていたのだ。アリスにスプラッタ系のホラー映画を見せられて、奉先が顔面蒼白になっている姿を。
そう。この奉先という少女、意外にホラー系グロ系への耐性が低いのだ。これならゲーセン歴の浅い僕でも、なんとかまともに彼女と戦えるはず……そう踏んだのである。
「いくら死体慣れしてるって言っても、本物の死体は動いて襲ってこないからね。こんなグログロしく緑色に光ったりしないし」
「だ、だから大丈夫だって言ってんだろ! あたしビビッてねえよ!」
ビビりがモロバレである。
奉先って腕っぷしは強い癖に、変なところで乙女なんだよなあ……。そこが可愛いんだけど。
「まあ、無理そうならやめてもいいよ? その場合僕が不戦勝ってことで」
「馬鹿にすんな。あたしも武将の端くれだ。挑まれた勝負からは逃げねえよ。『知者は時に後れず、勇者は決を留めず』ってな」
「なにそれ」
「好機を見定めたら、ビビらねえで行けって言葉だ。董卓(とうたく)っていう、昔のあたしの上司が言ってたんだけど」
そうは言いつつも、奉先の表情はやはり固い。格ゲーに興じていたときの余裕はどこへやら、青い顔で台に百円玉を投入している。
まあ、だからと言って勝負に手を抜くつもりはないけれども。
スタートボタンを押すと、「グエエ……」という謎のうめき声が響いた。
「は、始まったか……」奉先がごくりと息を呑む。
画面の中には、廃墟と化した研究所の一室のような光景が映し出されている。
ムービーを見るに、マッドサイエンティストの秘密実験によって生み出されたゾンビが、研究員たちを襲っては増殖し、研究所を乗っ取ってしまった――という設定らしい。
プレイヤーのふたりはその研究員の生き残りであり、手にした銃を頼りに施設からの脱出を目指す、というのがゲーム目的のようだ。この手のゾンビシューティングにはよくある筋書きだろう。
「なんでこいつら、果敢にゾンビに立ち向かおうとするんだよ……」奉先がため息をついた。
「え? だってガンシューティングって普通そういうゲームだし」
「だってさ。危険なゾンビの徘徊する施設内をうろつくくらいなら、助けを待つなり立てこもるなりした方が生存率上がるんじゃねえの」
「そんな弱腰な……。キミ本当に呂布奉先? 前に任務で吸血鬼の城に乗りこんだときには、『化け物退治だぜヒャッハー』みたいな感じだったのに」
「いや、吸血鬼とゾンビは全然違えだろ。強い弱い以前に、ゾンビはあのグロさが問題なんだ」
よほどゾンビが生理的に受け付けないのだろう。銃座を握る奉先の手には、すっかり力がこもってしまっているようだった。
「お、おい、一匹出て来たぞ!」
画面の中の通路の奥から、緑色のゾンビが這って進んでくる。実におどろおどろしい姿だ。「うう、キモい動き……。誰だよあんなの考え付いたやつ」
「でもまあ、シューティングの敵としてはイージーじゃない? あれなら落ち着いて狙えるし」
と、僕が銃のトリガーに指をかけようとしたその瞬間――。
ガタガタガタッ、と座席が振動を始めたのである。
奉先も予想外だったのか、「ひゃああああああああっ⁉」と奇声を上げてしまう。
しかし驚きは座席の振動だけに留まらなかった。背後のスピーカーから聞こえる唸り声。画面が突然反転し、突如別のゾンビの腐乱フェイスがどアップに映し出されたのだ!
「ひいいっ⁉」さすがに僕もビックリ。
驚く僕たちに追い打ちをかけるように、ゾンビ氏は腕を無茶苦茶に振り回してくる。
画面が赤くフラッシュし、僕と奉先はそれぞれライフゲージにダメージを受けてしまった。
「奉先、反撃っ! 反撃しなきゃ!」
「う、うおおおっ! 死ねええっ! 死ねやあああああっ!」
叫ぶ奉先と共にトリガーボタンを連打する。
さすがのゾンビ氏も、ふたりの銃弾の集中攻撃には勝てなかったらしい。哀れ首がはじけ飛び、動かなくなってしまった。
「くそっ」奉先が心底嫌そうに舌打ちする。「背後から不意打ち仕掛けてくるとか反則だろうがっ……! 男なら真っ向勝負で来やがれっ!」
「ゾンビにそんな男らしさを求めても……」
どうやら前方からゆっくり這ってくるゾンビは囮だったらしい。なかなか上手くプレイヤーの心理的な隙をついてくるゲームだ。油断できない。
「しかしこれ、気を抜いてるとすぐライフが尽きそうだね……。集中しなきゃ」
「わかってる。先にライフがゼロになった方が負けだからな」
その後、数体のゾンビに襲われつつもゲームは進行し、分岐点に差し掛かる。
画面の中には扉が二枚表示されていた。赤か青か、どちらかの扉を選択して進めということのようだ。
奉先がううむと唸った。
「こういうのって、片方が罠で片方が正解ルートとか、そういうパターンだよな……」
「だね。とはいえヒントも無いし、直感で選ぶしかなさそうだけど」
外れを選択したら、いったいどうなるのだろう。ゾンビの不意打ちとかトラップとか、その手の類のものだろうか。なかなかに緊張する選択肢だ。
「せっかくだから、あたしはこの赤の扉を選ぶぜ」
「まさかのコンバット奉先……」
そんな僕のボケをまるっと無視し、奉先の銃のターゲットが赤い扉を選択した。ぎいいっ、という鈍い音と共に、赤の扉がゆっくりと開いていく。
いったい何が起こるのだろうか。僕たちは身構えたのだが、
「……あれ? 何もない?」
画面に映るのは、倉庫のようなガランとした空間だけ。ゾンビに襲われるわけでもない。もしかしてこちらのルートが正解だったのだろうか。
ほっと安堵する僕の耳に、かさかさ、かさかさという妙な音が聞こえてきた。
「え、なにこの音」
「いや、音だけじゃねえ……」
何かが足の脛あたりを這いまわるような、妙な感覚に襲われる。このゾワゾワ感は、どうやら筐体下部の空気の噴出で表現しているようだ。最近のゲームってすごい。
いったいこれは何なのか。画面の下部を注視してみると、すぐにその正体がわかった。
かさかさと蠢く、長い触覚を持つあの害虫――。半分身体の腐りかけたGの群れが、部屋の床一体に敷き詰められていたのである。
「「ぎゃああああああああああああああああああああ!」」
奉先と一緒に、思い切り悲鳴を上げてしまった。
もうグロいとかそういうレベルを遥かに超えている。気が遠くなりそう。
ゾンビ犬とかゾンビカラスならまだしも、ゾンビGというのは斬新過ぎではないか。よくもここまで嫌悪感を掻き立てる造形をモデリングしたものだと、逆に感心するレベルだ。
そんな超絶リアルな腐れGが、こちらに向かって一斉に飛びかかってくる。
「む、無理無理無理! これは無理だろおおおっ!」
奉先が僕の腕に抱き付いてきた。
気持ちはわかる。いくら最強の武将とはいえ、彼女も年頃の少女なのだ。こんな光景を見て平然としていられるわけがない。
だがその一方、僕は違う意味でも平静を失いかけていた。
「ちょ、ちょっと奉先さん⁉ お、おお、おっぱいが腕に⁉」
「ああああああ! キモいキモいキモいっ! ふざけんなああああああっ!」
奉先さん大絶叫中。視界をガッチリと閉ざしながら大声で叫ぶ彼女には、僕の言葉などまるで耳に入っていないようだった。
そうこうしている間にも、ゾンビGの飛びかかり攻撃によって僕と奉先のライフゲージはガリガリと削られていってしまう。
「ほ、ほら奉先! ちゃんと撃たないとやられちゃうから!」
僕が耳元近くで叫んだことで、奉先はようやく我を取り戻したようだ。
「わ、わかってる!」と、奉先が片手で周囲を探りだす。目を閉じたまま、ガンコンを握ろうとしているのだろう。だがパニックのせいか、彼女の手は銃のグリップをつかむどころか、あらぬ場所へと伸びてしまったのである。
そう。僕の股間の方へ。
思わず「おおう⁉」と悲鳴を上げてしまう。
「あった!」奉先がつかんだのは、ズボンの中で自己主張していた僕のマグナムだったのだ。
「ちょおおおおっ⁉ それ違う! そっちの銃じゃないっ!」
「あれっ⁉ どこだ⁉ トリガーはっ⁉」
ミツキマグナムを執拗にまさぐってしまう奉先さん。ズボンの上からぎゅっと握られたり指で刺激されたり、手加減無しの行為であった。
妙な気分になってしまうではないか!
「ちょ、ちょっと⁉ なにするの⁉ マジで目を開いて⁉」
「出来るか! ゾンビのGなんて見たくねえんだよ!」
奉先は頑なに目を閉じながら、ミツキマグナムを操作しようと必死である。
腕には巨乳を押し付けられ、あらぬところは手で刺激され――。画面の中のライフゲージがどんどん減少していく一方、ミツキくんの性欲ゲージはどんどん高まっていく。
しかも焦った奉先さん、なんと適当に先端部分を連打するという暴挙に出るではないか。
「もうなんでもいいっ! 撃てええっ! 撃ちまくれえええっ!」
「や、やめっ……! 出ちゃうから! ホントにマグナム発射しちゃうから!」
ことここに至って、画面の中のゾンビGよりも隣の奉先の方が脅威であった。このままでは僕の尊厳が著しい損害を被ってしまう。
「死ねええ! 逝っちまええええっ! おらああああああっ!」
「あああああっ、い、イっちゃううううううううううううっ!」
快感と恐怖がせめぎ合う中で、僕は観念した。これはもうしょうがない。不可抗力だ。
全てを運命に委ね、発射カウントが十秒前に至ったその刹那。
突然ボックスのカーテンが開かれた。
「あのう、お客様。他のお客様から苦情が来ておりますので、もう少しお静かに……」
店員さんだ。女性の店員さんが声をかけてきたのだ。
「えっ?」奉先が僕の股間をまさぐるのを見て、店員さんが目を丸くする。
「えっ?」すっかり誤解をしている様子の店員さんに、僕も目を丸くする。
結論から言えば、僕は無様を晒さずには済んだ。
店員さんのおかげである。その代わり彼女には「店内ではそういう行為は禁止ですよ!」とキツく窘められてしまうこととなってしまったのだけれども。
「そりゃあまあ、『ガンコンと股間のマグナムを握り間違えた』なんて言い訳が、通じるわけもないとは思ったけど……」
ため息をつきながら、僕は踊る奉先を見つめていた。
「あのさ、隊長さん。あたしこれ、いつまで続ければいいんだ?」
「僕が飽きるまで」
「マジかよ」
正面モニターに流れる矢印を見つめながら、奉先がたどたどしくステップを刻む。彼女は今、レボリューション的なダンスゲームに挑戦中であった。
「これ罰ゲームだからね。頑張って踊ってね」
先ほどのホラーガンシューでは、慌てふためいている間に、僕も奉先も揃ってライフゲージがゼロになってしまった。どちらが先に尽きたのかはもはや判別できなかったが、怯え度合で言えば奉先の方が遥かに上だったことは言うまでもない。なので判定と協議の末、勝者は僕ということになったのだった。
「こんなのあたしの柄じゃねーよ。ったく……」
もちろん奉先にはただダンスを命じたわけではない。衣装として、フリフリでキュートなミニスカメイド服を着用させているのだ。
「だいたい、なんでこんな服がゲーセンに置いてあるんだ」奉先が顔をしかめる。
「プリント写真機用の貸し衣装だってさ」
普段のスリット全開チャイナも相当アレだが、メイド姿の奉先もかなりエロい。エプロンの上の乳袋はぷるんぷるんと揺れ、フリル付きのスカートからはチラチラと白い下着が覗いている。意外と萌え系エロスもいける子なのだ。
「正直、こういう格好を隊長さんに見られるのは結構恥ずかしいんだけどな……」
「いや、他のお客さんたちも見てるみたいだよ?」
「余計恥ずかしいっての!」
「そうは言うけどさ、奉先。こういう羞恥プレイ的な命令も大好きでしょ」
「うっ……」と口ごもる奉先。
赤く染まった彼女の表情はなんとも魅力的だった。このドM娘め。
ちなみに後日、こうしてミニスカメイド服で踊る奉先の姿が、有志の手でネット掲示板にアップされていたらしい。〝グラップ潰しの奉先さん〟のお茶目な姿に、ネット上ではさらなるファンが生まれてしまったようだ。
おかげで奉先も、ゲーセンでナンパに遭う回数が増えたとかなんとか……。
つくづく人気者だなあ、奉先さん。