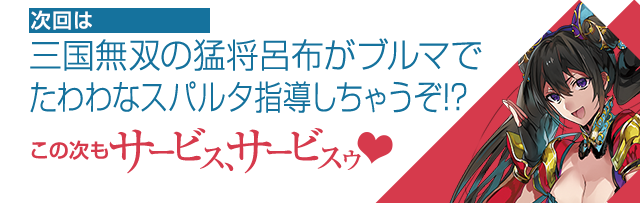時震の影響でおかしくなった歴史を修正する。
それが僕たち航時局歴史管理課、通称THRのお仕事。
THRに籍を置くエージェントは、僕を除けば様々な時代からやってきたプロフェッショナルな偉人ばかりだ。近代ヨーロッパの皇帝陛下だったり、古代中国の武将だったり、アメリカの発明王だったり。
現在僕の隣の席に座っている背の小さな女の子――アリスも、世界にその名を知られたギリシャの哲学者、『万学の祖』アリストテレスなのである。
「で、なんで御戸(みと)さんがここにいるんです」
切れ長の銀の瞳が、僕をじっと射竦めた。
身長およそ一四〇センチの少女体型。真っ白な肌にシルバーブロンドという、アンティーク人形めいたルックスの持ち主である。制服の上に羽織ったケープも、とても知的で上品な印象だ。ぱっと見だけなら、物憂げな美少女という雰囲気かもしれない。
憎まれ口さえ叩かなければ、の話だが。
「休みの日にまで私につきまとうなんて、まるでストーカーですね。そんなに児ポ法の厄介になりたいんですか。このロリコン野郎が」
いつものごとくに罵声を浴びせられ、僕は「うっ」とたじろいでしまった。
ああもう。こうやって口さえ開かなければ、本当に可愛い女の子なのに……!
「いや、アリスって休日は何してるのかなーって気になってさ。一応隊長として」
「暇人なんですね」アリスが肩を竦める。「別にあなたが何をしていようとどうでもいいですけど、くれぐれも邪魔はしないでくださいよ。これから日課の研究活動に励む予定なんですから」
言いつつ彼女は、机の上に広げたノートや本を指し示す。
アリスもいちおう学者らしく、こうして日々研鑽を重ねていたというわけか。ただまあ身長的にミニマムな彼女がこうして机に座っていると、研究活動に勤しむ学者というよりは、宿題を始めようとしている小学生にしか見えない。ちょっと微笑ましかった。
「こっち見つめながらニヤニヤしないでください。気持ち悪い」アリスが鼻を鳴らす。
「ごめん。でもアリスの休日って、アニメ鑑賞で終わるもんだとばっかり思ってたよ」
「ひとを何だと思ってるんです。これでも私、仮にもギリシャの大哲学者ですよ」
アリスが呟くと、会議室の上座から「ははは」と笑い声が聞こえてきた。
「いやいや、アリスは哲学者としてはまだまだヒヨっこだよ。いかに〝博識〟だろうと、対話と実践の能力が著しく欠けているからね」
軽やかな短髪に精悍な細面。びしっとしたダークスーツの似合うカッコイイこのお姉さんは、アリスと同様に古代ギリシャからやってきた哲学者、プラトンさんだ。
「まあ、その辺を補うために、私がこうして補習をしてやってるわけだけど」
彼女はアカデメイアなる学校を仕切る学長さんであり、航時局に籍を置く先輩エージェントでもある。アリスにとっては色々な意味で先達に当たる方なのだ。
プラトンさんもなかなかに忙しい方のようだが、そんな多忙な日々の合間を縫うようにして、時々こうして弟子のアリスに補習授業をしているらしい。なんとも教え子思いの先生だ。
「さて、じゃあ今日の授業を始めよう」プラトンさんが口を開いた。「ミツキくんも来てくれたことだし、今回は実践形式でやってみようか」
「はあ、実践形式……。アレをやるわけですか」アリスが舌打ち交じりに僕を一瞥する。
アレってなんだろう。ただの見物人である僕には、なんのことやらさっぱりわからなかった。
「すいませんプラトンさん。この授業って、どんなことを行ってるんですか」
「ああ、ミツキくんにはちゃんと説明しておかないとな」
プラトンさんが薄い笑みを浮かべる。
「まあ、わかりやすく言うと、私たちは今『純愛ラブコメにおけるヒロイン力の研究――兄妹愛編』なんてものを研究しているんだけど」
「は? 純愛ラブコメ? 兄妹愛?」
哲学とはまったく無縁そうなワードの登場に、思わず首を捻る。
そんな僕を見て、アリスが「やれやれ」と鼻を鳴らした。
「やはり御戸さん程度の哀れな知能では、私たちの崇高なテーマは理解できませんか」
「そりゃわかんないよ。なんで哲学者が顔を付きあわせてラブコメ云々の研究してるの」
「そもそも御戸さん。プラトン先生の〝イデア論〟くらいは知っていますか?」
「イデア論……。ああ、ええと、名前だけは聞いたことくらいはあるような」
「我々の認識する事物や世界は不完全なものに過ぎず、形而上学的な世界に完全な理想形(イデア)が存在するという考え方です。イデアこそ真実であり、現実は虚像に過ぎないと捉えるわけですね」
「はあ……?」
ダメだ。さっぱり意味がわからない。そもそも哲学者様の考えることを、凡人が理解しようという方が無理なのかもしれない。
「ごめんアリス、普通のひとでもわかるようなレベルで説明してくれない?」
「そのつもりで言ったんですけどね……。これでダメなら、もうお猿さん向けの説明に切り替えるしかありませんよ」
「お猿さんでいいから」僕はプライドを投げ捨てた。
「要するに、『三次元はクソ、二次元最高』って考え方ですよ。これがイデア論です」
「またえらく乱暴にまとめてきたね⁉」
「だってプラトン先生ってそういうひとですから。ああ見えて、二次元に理想(イデア)を見出しちゃってますから」
「うっそだー……」
「ホントですよ。その証拠に、この授業の教科書だってほら」
アリスの前に置かれていた本を手に取り、じっくりとよく見てみる。
難解な哲学書の類だと思っていたそれらの表紙には、なにやら可愛らしい美少女キャラクターのイラストがふんだんに描かれていた。『大好きなお兄ちゃんがなんたらかんたら』とか『妹が魔王でどうのこうの』とかそういうやつ。
「ラノベじゃん! しかも全部妹萌え!」
アリスだけでなく、まさかその師匠までソッチの世界の住人だったとは驚きである。
当のプラトン先生に目を向けると、「なにか問題が?」とでも言うかのような涼しい顔をしていた。
「別に驚くことはないだろう、ミツキくん。私がアリスを育てたんだから」
それはもう、一発で「ああ……」と納得してしまう言葉だった。なるほど、この師匠あって、この弟子ありというわけか。
「アリスが妙にアニメとか好きなのって、プラトンさんの影響だったんですね……」
「二次元こそ魂の還るべき場所だよ。その考えを世界に広めるために、私はアカデメイアを設立したと言っても過言ではない」
プラトンさんが口角を吊り上げる。
ひとは見かけによらないものだ。クールで知的なお姉さんかと思いきや、彼女もなかなかにディープな方だったようである。
プラトンさんが「そういうわけで」と続けた。
「今日はアリスに、これまで学んできたことを実践させる機会を与えよう。ミツキくん相手に、存分に妹キャラとしてのヒロイン力を見せつけるといい」
「この男を相手に、ですか」アリスさん、大変嫌そうに顔をしかめてしまう。「御戸さん相手にヒロイン力をアピールとか、正直ヘドが出ますね」
「だからいいんじゃないか。簡単に出来たらつまらないだろう?」
「はあ……。まあ先生がやれと言うならやりますけど」
ようやく僕も状況が飲みこめてきた。プラトンさんは、アリスがどれだけ『妹萌え』を理解しているか、僕を実験台に推し量ろうとしているのだ。
「やっぱ哲学者って、どっかおかしい……」
ため息をつく僕をよそに、プラトンさんが説明を続ける。
「制限時間は十分。アリスはその間に、可能なかぎりの妹アピールを行うんだ。時間内にミツキくんを興奮させることが出来れば、合格だと認めよう」
「御戸さんが興奮しているかどうかの判定基準は?」
「そうだなあ」プラトンさんが僕の下半身に目を向けた。「彼の股間のバーの上下で判断すればいいんじゃないか? 百パーセントのフルチャージ状態にさせられたら合格ってことで」
気づけば僕の股間は、勝手に採点用のバーにされてしまっているようだった。
なんだか納得いかない。さすがにひとこと物申したい気分だ。
「いや、ちょっと待ってくださいよ? 僕、付き合うなんて言ってませんよ?」
「なんだよミツキくん。せっかくのアリスの試験なのに、協力してくれないのか?」
プラトンさんが眉をひそめる。
「残念だ。キミが協力してくれないなら、フレドリカにはこう言うしかないな。『彼は薄情なヤツだった』って」
「うっ……」言葉に詰まる。
そうだった。プラトンさんとフレドリカさんは、仲のいいお友達同士なのだ。
フレドリカさんの好感度を上げるためには、まず彼女に気に入られておくに越したことはないだろう。将を射んとする者は……の精神である。
「了解しました。喜んで協力させていただきます」素直に頭を下げた。
プラトンさんはにやりと口の端を歪め、
「ちなみに、ミツキくんがあっさり簡単に興奮しちゃった場合でも、フレドリカにはきっちり報告するつもりだからね。『あいつは堪え性のないスケベ野郎だ』って」
「適当にお茶を濁すわけにもいかないってことですか……」
さすがはプラトンさん。アリスの師匠だけあって、Sっ気たっぷりなお方だ。
これは何が何でも興奮するわけにはいかない。鉄の意思で堪えねば。
「いいでしょう。男、御戸ミツキ。受けて立ちますよ。アリスごときの誘惑には負けません。フレドリカさんへの愛の深さを思い知らせてやりますから」
「へえ。言うじゃないですか。ロリコン風情が」アリスが眉をひそめた。
「ようし、準備はいいかい」プラトンさんが壁の時計に目を向ける。「じゃあ今からスタートだ。アリス、実技に入って」
アリスは「わかりました」と頷くと、おもむろに席を立ちあがった。
身構えている僕の肩に手を置きながら、膝の上にちょこん、と跨る。何をする気だろう。
「ん? ええと、アリスさん?」
ごくり、と喉を鳴らしてしまった。
太ももに感じる小さなお尻の温かさは存外にこそばゆく、それだけでドキドキしてくる。
だがこの御戸ミツキとて、数々の修羅場を乗り越えてきたTHRエージェントだ。これしきのことで動揺など――。
「えへへ……お兄ちゃん」
思わず「ぐはあああああああっ⁉」と驚愕の叫びを上げてしまった。
アリスが笑った! 上目遣いに僕を見上げながら、「お兄ちゃん」呼びで微笑んだ!
口を開けば毒舌しか出てこないような小娘が、こんなにも優しそうに頬を緩めている……。なんというレアな光景だろう。完全に不意打ちだった。文句なしのクリティカルヒットである。
「ア、アリスもそういう可愛い顔出来たんだ……」
「当たり前だよ。アリス、お兄ちゃんのこと大好きだもん」
「おうふっ……!」衝撃のあまり、喉から変な声が出てしまう。
何この口調。この子本当にあのアリスなの? 天使かなんかが降臨してるんじゃないの?
「ねえお兄ちゃん。アリスね、お願いがあるの」
「お、お願いって……?」
「お兄ちゃんとね、チューしたいなって」
「チュ、チュウゥゥゥッ⁉」
「だめ、かな?」
アリスが頬を染めて見上げてくる。潤んだその唇は、まるで薔薇のつぼみのように魅力的。何もかも忘れて吸い付きたい衝動に駆られてしまう。心臓はもうドキドキバクバクだ。
「お兄ちゃんになら、アリス、全部あげちゃってもいいんだよ……」
もはや普段の毒舌娘の面影はない。これがアリスの学んできたヒロイン力なのか。こんな至近距離で見つめられたら、股間のJr.も興奮の一途である。
僕は深呼吸をしながら、
「あ、あのねアリス? お兄ちゃんと妹は普通チューしないんだよ?」
「普通はそうだけど……でも、アリスとお兄ちゃんは普通の関係じゃないもん」
アリスはそんなことを言いつつ、僕の股間をさわさわと撫で付けてくる。そのあまりに突然の刺激に、僕は「ふおおおおおおっ⁉」と身悶えてしまった。
「プ、プラトンさん⁉ これ反則じゃないんですか⁉ もう純愛ラブコメのレベルを軽く振り切っちゃってる気がしますよ⁉」
「そんなことはないぞ」プラトンさんが首を振った。「最近の作品では過激な描写も多いからね。実妹と結ばれるなんてよくある話だし……。キミたちがこの場で行きつくところまで行ったとしても、私は一向に構わない」
「そこは構いましょうよ⁉ なにを考えてるんですか⁉」
声を荒げる僕に、プラトンさんが「まあまあ」と微笑みかける。
「『自分に打ち勝つことが最も偉大な勝利である』――これは現代にも残っている私の言葉なんだけどね。ミツキくん、今キミは、そういう自分の性欲との戦いに直面してるわけだよ」
「は?」
「こんな困難を乗り越えられない男に、フレドリカが振り向くと思うかい? 男なら、正々堂々アリスの誘惑に立ち向かうべきなんじゃないかい?」
「そ、そんなこと言われても――」
プラトンさんの意味不明な詭弁に文句を言おうとしたのだが、それは出来なかった。その前にアリスの唇が、僕の唇を塞いでしまったからだ。
「れろ……ちゅっ」
なんの遠慮も躊躇も無く、アリスの小さな舌が侵入してくる。
「んんんっ⁉ んんっーーーー!」
「ちゅっ、れろ、ちゅうう……」
アリスは積極的だった。まるで僕の中をとことん味わおうとするような、情熱的な口づけである。
「お兄ちゃんっ……ちゅっ、んん、好きっ……れろっ、大好きっ……!」
舌を絡ませながら、アリスがそんな愛らしいことを言う。
アリスとのキスは初めてではないけれども、なぜかものすごく新鮮な気分である。「お兄ちゃん」呼びがそうさせているのだろうか。
頭ではフリだとはわかっているのに、身体はなぜか抗えない。おかしい。僕はロリコンとかシスコンとか、その気はないはずなのにっ……!
アリスが「ぷはあっ」と顔を離す。彼女はいつになく切なげな表情を浮かべながら、自らの濡れた唇を指先で撫でつけるのだ。
「アリス、お兄ちゃんとなら、この先をしてもいいかな――なーんて」
「ぐうっ……なんという苛烈な攻撃……」
だが、僕はまだ負けていない。股間のバーの充填率はギリギリ九割ほどだ。僕の理性が、最後の一線だけは死守しているのである。
「お兄ちゃん、アリスじゃ気持ち良くなってくれないの?」
「ぼ、僕の精神力を舐めないでいただきたいっ! 兄妹ゴッコで興奮するほど、ヤワな鍛え方はしてないからねっ!」
「ははは。ミツキくんは、お姉さん属性寄りだもんなあ」
プラトンさんが笑みを零す。ええその通りです。理想はフレドリカさんなんです。
所詮アリスはセクシーからは程遠い小娘だ。いくら美少女だとはいえ、こんな短時間で篭絡されることなどあるまい――。僕はそんな風に高をくくっていたのだが、
「じゃあお兄ちゃん、ちょっと目を瞑っててね」
「え?」と問う暇もなく、アリスの左手が僕の視界を塞いでしまう。いったい何をするつもりなのか。耳に聞こえてくるのは、するりという衣擦れの音だけだ。
ややあって、手のひらにぽふん、と何かを押し付けられてしまう。柔らかくてすべすべで、ほのかに温かい布状の物体――コレはいったい?
「ね、ねえアリス? あの、なんなのこれ?」
「わかるかなあ? ヒントは、『アリスが今日一日、ずっと身に付けていたもの』でーす」
手の中の布を握りしめながら、僕はごくりと息を呑んだ。アリスが一日身に付けていたもの――。女の子が身に付けるもので、かつ、手のひらに収まるサイズの布と言えば、僕にはもうアレしか思い浮かばない。
「ま、まさかこれって、パ、パ、パンっ――」
「アリスのお気に入り、お兄ちゃんにあげる。いつでも好きに使ってね」
そんなことを言いながら、アリスが「よいしょ」と再び僕の膝の上に腰を下ろした。ズボン越しに感じる柔らかな感触。僕が手にしている布が想像通りの代物だとすれば、いまアリスはそのスカートの下に何も穿いていないわけで……。
「こ、これはアカンっ……!」
「あ、大きくなった」
そう。彼女の言う通り、僕のJr.は全力全開のフルパワーモードへと移行していた。ズボンを押し上げ、ことさらに存在感を主張してしまっていたのである。
だってまさか、アリスがこんな過激なプレイに出るとは思わなかったんだもの!
「ええと、これって僕の負けなの……?」
「はっ、ざまあないですね」
視界を覆っていたアリスの手が取り払われる。
目の前の彼女は、普段通りの冷笑を浮かべていた。
「これしきの行為で陥落してしまうなんて、やはり御戸さんはどうしようもないロリコン野郎ですよ。フレドリカさんへの愛とやらはどうしたんです? ハンカチひとつで雲散霧消ですか」
「え、ハンカチって……」
手のひらに目を向けてみれば、そこにあったのは花柄レースの刺繍の入った、白いシルクのハンカチだ。僕が想像していたものとはまるで違う。
「あれ? もしかして御戸さん、なにか別のものだと誤解していたんですか? もしかして、脱ぎたてのなにかを想像していたんですか?」
「ううっ……。だ、だってアリスがあんな思わせぶりなこと言うから……!」
「バカじゃないですか」アリスが鼻で笑う。「御戸さんなんかに、私がそんなもの軽々しく手渡すわけがないじゃないですか。発想からしてホント最低ですね、この屑野郎は」
僕には反論することさえできなかった。アリスってばもう! すっかり騙されたよ!
「三分五十秒か。なかなかのヒロイン力だね」
プラトンさんが時計を見ながら、満足げに頷いていた。
「しかし、アリスもやるもんだね。ハンカチの一件はともかく、まさかあんな甘ったるい声でミツキくんを誘惑するなんて」
「もっとも効率のいい手段を取っただけですよ。御戸さんは、なんだかんだ言って純粋無垢な少女には目がない変態ですから。『ランドセル』とか『たて笛』とか、そういう単語に邪な感情を抱いてしまうくらいにはダメなひとですから」
アリスの根も葉もない中傷に、僕は「そんなことないよ⁉」と口を挟む。
プラトンさんは、ふふっと薄い笑いを浮かべながら、
「アリスがポテンシャルを引き出せたのは、相手がミツキくんだからこそ、なのかな」
「はあ?」アリスが眉をひそめる。
「なんだかんだ言ってアリス、『お兄ちゃん大好き』って言ってたアレ、まんざら演技じゃなかったんだろう?」
「何を言ってるんですか先生。あなた目が腐ってるんですか」
師匠に対してもこの物言い。やっぱりアリスはアリスだった。あの天使めいた妹キャラは偶像に過ぎなかったのである。
「理想(イデア)こそ真実だっていう話……。なんか信じたくなってきた気分」
プラトンさんが「ともあれ」と僕に向き直った。
「結果はアリスの圧勝だったね。ミツキくんは堪え性のないスケベ野郎だって証明されちゃったわけだ」
「や、やっぱりフレドリカさんには報告しちゃうんですか?」
にやりと笑うプラトンさんの表情には「当然だろ」と書いてある。
なんてこった。最近フレドリカさんの中で下降気味だった僕の株が、ますます下落していく予感……。手の中のハンカチを握りしめながら、僕は自らの自制心の無さに呆れかえっていた。
アリスが「それでは先生」と口を開く。
「このまま次のステップに進んでも構いませんか」
「そうだな。ミツキくんの股間も苦しそうだし……。次の実践に入ろうか」
次の実践……? 不穏な響きである。
「あの、次の実践って?」
「兄妹愛編その2だ」プラトンさんが白い歯を見せて笑う。「『エロコメディにおける兄妹恋愛の描写限界についての考察』――なかなかに哲学的な命題だろう?」
「どこが哲学的なんですか⁉」
そんな僕のツッコミも空しく、実技は再開されてしまう。
なんとアリスさん、僕のズボンのジッパーを勢いよく下ろしてしまったのだ。
「ちょ、ちょっとなにしてんのアリス⁉」
「それは言えませんね」
「なんで⁉」
「『描写限界についての考察』だと言ったでしょう。察してください。小説本編ならまだしも、全年齢が幅広く閲覧するであろうこの媒体では、おいそれとその行為を口に出すことが出来ないんですよ」
「全年齢版で口に出せないようなこと始めちゃうの⁉」
「ええ。まあ、とりあえず――」
アリスは再び天使のような笑みを浮かべながら、小悪魔めいたセリフを口にする。
「アリスで気持ち良くなってね、お兄ちゃん♡」
なにも言葉を返すことが出来なかった。
どうやらアリスとのエッチな兄妹ゴッコは、いぜん続投の模様。正直、たまりません。
自分に打ち勝つことが最も偉大な勝利である――。プラトンさんはそう言っていたけれど、残念ながら僕が勝利を収める日はまだまだ遠そうだ。