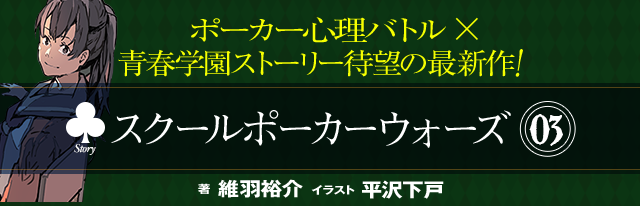


第3章 2/2
「……赤村くん?」
「決定に口は挟みません。姉御の判断には従います」
その言葉とは裏腹に、赤村の表情は奇妙に歪んでいた。
「ただ、純粋に疑問なんです。最初に市内対抗戦の話が出た時、姉御は『中学生が行うイベントでお金を賭けるのは好ましくない。その悪しき風習を絶ちたい』と言いましたよね。それはどうしてですか?」
虚を衝かれた隊長の表情が固まった。
「姉御は合理主義者です。常にメリットとデメリット、リスクとリターンを天秤に掛けて行動しているし、それはモンスターズの大将として頼もしい事だと思っています。その姉御にとって、プール金を解体するメリットは何ですか? どういうリターンがあるんですか? 俺にはそれが分からないんです。……中学生が金を賭けてはいけない、なんて説明がおためごかしである事くらいは俺にも分かります。姉御は、その必要があれば平然とお金を賭けられる人でしょう? その姉御が、多少の危険を冒してでもプール金を解体したいと考えている。じゃあ、それはどうして、って思ったんです。……思えば過去にも同じような事がありました。あの時は隊長の事をよく知らなかったから、深く考えませんでしたが」
赤村が一瞬黙り込み、記憶を辿る。
しかし、その瞳はじっと隊長を捉えている。
「あの日。ヘッズアップ三本勝負でコテンパンにされたあの日、やっぱり同じように疑問だったんです。勝負を終えてモンスターズに入る事が決まって、姉御と浦原が帰った後、少しだけファットマンで考えていたんです。なんであの女は、王座戦で倶楽部を倒したいんだろうって」
結局聞けず仕舞いでしたが、と赤村は言い添えた。
隊長は長いこと無言だった。
第五自習室の窓から差し込む黄昏は既に地平線へと落ちていて、部屋の中は薄暗い。廊下にあるはずの蛍光灯のハム音がやけに大きく聞こえた。
「ごめん」
余計な事は言わなくていいと思った。
だが自分には、隊長がこれから何を言おうとしているのか、手に取るようにはっきりと分かった。
「できれば言いたくないから言わなかった。合理的であれ、論理的であれ、と常々言ってきたわたしが、大きな矛盾を抱えている事が知られちゃうからね。でも、ここにいるみんなには知る権利があるし、わたしには説明する義務があると思う。赤村くんの疑問にも、どうしてわたしがプール金を解体したいと考えているのかも、たった一言でここにいるみんなが理解できると思う」
技術家庭で誰かが作った壁掛け時計は十七時二十六分を差していて、吹奏楽部が演奏するキャラバンの到着が聞こえてくる。長い長い会議の果てに第五自習室の窓は結露で白く染まり、向こう側に見えるはずの住宅街の灯りはぼんやりと闇に溶けている。
そして隊長は、あの台詞を口にした。
「────十年前に存在した伝説の一代目、桜庭諒太はわたしの兄なんだ」
それを言ってしまえば、隊長はもう止まる事はできない。
「木佐さんからプール金の事を教えてもらって、少し考えたの。違法に集められたプール金が膨らめば膨らむほど、誰かが悪用しようと考える。最初は上手くいくかもしれない。その次もその次もそのまた次もうまくいくかもしれない。でも、時間が経てば経つほど、いつかどこかで何かをやらかす可能性は高まっていって、やがては誰かがババを引く事になる。わたしは博愛主義者を気取るわけでもないし、その誰かが罪を償うのは当然の事だと思う。でも、もしも今、その萌芽を摘む事ができるのなら、それはわたしがやるべき事なんだって強く感じた。……それだけの話。それだけの話にみんなを巻き込んじゃった」
隊長はまだ、大事なことを隠している。
それを言ったらこの場にいる面々の客観的な判断力を削ぐ事が分かっているから、隊長は一番大事なことを言っていない。
プール金は第二の兄を生み出してしまう可能性があると、隊長はそう言っていた。
隊長の兄は金に目が眩んで政府未認可の電脳カジノに入り浸って数千万円を稼いだが、その代償は大きかった。警察に捕まり、休学した後に転校し、家族は離散し、隊長は未だに兄とほとんど会えないと聞く。そして隊長の兄が稼いだ数千万円と同じように、プール金はいつか誰かに壊滅的な打撃をもたらす。そして、その誰かにもきっと家族がいるはずだ。そこまで考えれば赤村でも分かる。隊長がプール金解体を主張した理由はたった一つだ。
自分と同じような目に誰かを遭わせたくなかったから。
「────やろう」
もちろん勝算はなかった。
東本郷中学校はプール金集めに積極的に関与していたし、当時のポーカー審議会が資金不足からプール金を胴元にした賭けを他校に強制させて、長年にわたってプール金を掠め取っていた経緯がある。
だから他校の言い分も理解できる。
必死でかき集めたプール金を散々掠め取ったお前らが、今さらプール金を解体したいなんて意見が通るかという主張も理解できよう。王者気取りのわがまま野郎に王座戦挑戦状を突きつけて狼狽させてやりたいという感情も理解できよう。
だが、だからと言って金の絡む物事はいずれ腐敗を招くという隊長の主張が間違っているわけではないし、その主張の根底にある隊長の感情が正当性を失うわけではない。
椅子に座ったまま、腕を組んで隊長をまっすぐと見つめる。
「俺は王座戦を受けて立ちたい。例えプール金を解体できないとしても、だ。ここで退いたら最後、俺達はプール金について介入する機会を永遠に逸する。それに逆の視点から考えてみろ。市内対抗戦に優勝すれば、出場校は有力プレイヤーを一気に失う事になる。それは交渉のカードとして使えるはずだ」
心の底ではプール金なんて所詮は他人事だと思っていた自分を恥じるのは後にすべきであろう。
「敵は俺達が王座戦を受けて立つとは露ほどにも思っちゃいない。市内対抗戦までは二週間あるんだ。今、俺達が準備を始めれば、その分優位に戦えるはずだ」
「複数の王座戦挑戦状を叩き付けられた例はないんだぞ。どうやって戦術を立てるつもりだ」
「このまま撤退すればあたし達の学校だけは逃げ切れると思うよ。それでもやるの?」
「前例主義と先送り主義について語りたいなら廊下でやってくれ」
榊原と木佐に指を突き立てる。
榊原がものすごい顔で睨みつけてきたが、榊原はいつもこんな顔なので慣れっこだ。部屋中の人間が自分の方を向いているかと思ったら、小此木だけは漫画に熱中していて自分の声など聞いちゃいなかった。
「浦原に賛成だ」
類人猿のお友達が掌に拳を叩き付けた。
「姉御の考えは筋が通っています。辞退する必要なんてないはずだ」
柳は腕を組んだまま窓ガラスの向こう側を見ていた。
「……榊原くんはこの事を知っていたのかな?」
「小林委員長からの引き継ぎでな」
「そうか。それならよかった。────妙ちゃん、どうして今まで言わなかったの?」
「……感情論ってわたしの中でもっとも恥ずべき思考回路だから」
柳がふっと笑った。
「そんな事はないさ、人間味のある考えで逆に安心した。僕はこれまで妙ちゃんの事を論理のみで動くプレデターみたいに思ってたから」
「今は?」
「感情でも動くプレデター」
この会議が始まって以来ずっと塞ぎ込んでいた隊長が、その言葉でようやく笑った。
柳はコルクボードに貼られた紙を摘まんで次々と引っ張った。ぴりぴりと破いた紙を丸めてポーカーテーブルに落としていく。
「僕はただ単に王座戦を受けるのは反対だが、それに見合うメリットがあるのなら話は別だ。王座戦は一旦脇において、プール金を解体できないかという観点で少し考えてみよう」
待ってましたとばかりに、各々が持論をぶちまけようと口を開いた。
「要はプール金を解体すればいいんだろ? 多少暴力的な考え方でも構わないんじゃないか? 各校のポーカー審議会に『渉外連絡会がプール金を隠し持っている』ってたれ込むとか」、「駄目だ。その金を巡って各校が骨肉の争いを繰り広げる事になって、いずれは教育委員会の耳に入る」、「それならいっそ、教育委員会にたれ込むってのはどうだ? 東本郷中のポーカー活動保護を条件に、教育委員会に告発しちまうとか」、「教育委員会はそういう政治的な駆け引きには応じてくれないだろう。判明した時点で明浜市のポーカー活動が完全禁止になっても何ら不思議じゃない」、「同感だな。忘れるなよ、教育委員会は今も中学校でのポーカー活動を禁止にしたいと手ぐすね引いているんだぜ」、「今いる渉外連絡会全員に分配するって提案はどうだ。当初の目的とはずれるが、プール金を解体する事は可能だぜ?」、「渉外連絡会は六人で構成されていて、それが七校か。三〇〇万円を四十二人で分けるとえーと、一人七万円ちょっとか。現実的な提案かも」、「待って待って。これまでプール金を作り続けてきたOBがそれを知ったらどうなると思う? OBは失うものがないから、それこそ大問題に発展しちゃうよ」、「あのさ……」
これまで議論に加わっていなかった柳がぽつりとつぶやいた。
「プール金解体という観点から考えてみようって言った僕がこれ言っちゃうと、そもそも論になっちゃうんだけどさ、」
柳はまるで、正義か悪かで言うと明らかに正義側に立っていますみたいな澄ました顔で、少し気恥ずかしそうに微笑んだ。
「三〇〇万円のプール金、……僕らがもらっちゃおうか」
第五自習室が爆笑の渦に巻き込まれた。
笑いの渦はゆっくりと熱を帯びた欲望と抜け目ない計算を孕み、窓に飾られている観葉植物が浄化した空気をゆっくりと澱ませていく。押し黙った面々は乾いた笑顔を貼り付けたまま、互いを探るように視線を交わしている。
きっと、誰もが同じ事を考えている。
プール金解体が受け入れられないのであれば、俺達がプール金を丸ごと奪ってしまおう。
それはいざ頭に浮かべてみると、意外なほど論理的な発想だった。
「でも……どうやって?」
隊長は前置きを省いて柳に尋ねた。
柳はいつものように臭い笑顔のまま、とある人物を見つめている。漫画に夢中でこちらの話を聞いている様子など一切見せてはいなかった癖に、柳に見つめられた途端、小此木が漫画本をばたんと閉じた。
「皆さんが静かになるまで2.8秒かかりました」
「小此木先生」
急に柳がかしこまった。
「先生、何か秘策が……?」
「ない!」
ねえのかよ。
しかしその言葉とは裏腹に、小此木は立ち上がって後ろ手で第五自習室を歩き始めた。
「でもようやく面白くなってきましたねえ。隊長の悲しい告白、浦原くんの熱い主張、賛同する仲間たち。ぼくはこういうの結構好きなんです」
この発言は残念ながらまるっきりの嘘だ。恐らく、この場にいる全員がそれを理解している。
「ぼくは隊長の心意気に感動したよ。ポーカーモンスターズの末端に籍を置くぼくとしても、なんとか隊長の助けになりたいと────」
「小此木、今は真面目な会話をしてるんだぞ」
赤村が窘めて、小此木は無邪気な笑みを浮かべた。
「あはは、うそうそ。ごめんなさい。本当はね、大事にしているプール金を奪い取られそうになったら、彼らがどんな顔をするのか見てみたいなあって思ったんだ。度肝を抜かれた人間ってどういう表情をするのかな。心底やばい問題に片足突っ込んじゃったと気付いた時、どういう反応をするのかなあって」
多分、こいつにとって渉外連絡会や市内対抗戦出場校のプレイヤーなんてものは、屋上のプールで凍らせようとした魚と大して変わらないのだ。
「秘策はないけど、提案はあるよ。でも、それはきっと隊長にとって嫌悪感を覚える選択肢だと思う。客観的には違っても、主観的には隊長もぼくやお兄さんと同類になってしまう。悪者になっても、罪悪感に押し潰されたりしない? ぼくはそれが心配だ」
にやにやしながらそう語る小此木に隊長は即答した。
「覚悟はできてる」
「じゃあ、融資してあげるよ。三〇〇万円」
小此木はいきなり本題をぶちまけた。
第五自習室が静まりかえるのは何度目だろう。小此木の「くふふふふ」という気味の悪い笑い声だけが響くなか、柳が目を瞑ったままテーブルを指で叩いていた。
計算しているのだ。
「────多分、彼らは応じる」
目を見開いた柳の表情は、確信に満ちていた。
「最初は呆気に取られるはずだ。それからしばらくして怒号が鳴り響く。今さら金を賭けるなんてずるいって。────そうならないようにお金を賭けたいと説明し、採択を取ってもらった方がいい。会話誘導は妙ちゃんならできるよね?」
隊長はじっと考え込んでいる。
隣にいた木佐がおずおずと手を挙げた。まるで授業を聞いていなかった生徒のようにばつの悪そうな顔で、
「ねえ、話の流れが見えてなくてごめんね。三〇〇万円ってどういう事?」
「俺も知らんぞ。何でそんなもんを小此木が持ってる」
木佐と榊原が呈した疑問はもっともなものだったので、簡単に補足する。
「簡単に言うと、七月に起きたMr.Ogre事件の真犯人が小此木だからだ。こいつは電脳カジノで儲けた金をたんまり持ってる」
「────なっ!?」
絶句している榊原を無視して柳に尋ねる。
「採択で可決されない可能性は?」
「東本中が金を賭ければ、プール金に関して二度と文句は言えなくなる。彼らはすぐにそう考えるはずだ。採択に持ち込めば可決される可能性は極めて高いと思う。……ただ、満場一致の中で三〇〇万を賭けると言ったとしても、彼らは呆気に取られた後、プール金が全額奪われるかもしれないという恐怖から怒り出すと思う。でもしばらくは静かに耐えるんだ。いずれ誰かが気付く。『三〇〇万という金額にビビったが、こいつらが優勝できる確率はかなり低い』って事に」
その言葉に木佐が眉を顰めた。
「どういう事?」
「僕らはもちろん出場校の中では一番強い。でも他の六校全員が協力した場合、僕らの勝率は極めて低くなる。だから一旦、会議を休憩して象の鼻中学校の渉外連絡会と各校の渉外連絡会の委員が話し合う。そこで彼らは落ちている金を拾うようなものだと結論づけ、しぶしぶといったふうを装って応じるはずだ」
「で、俺達は勝てるのか……?」
王座戦を受けて立とうぜ! と言ったばかりなのに急に弱気になって恐縮だが、しかし三〇〇万を賭けるなんて話は、まるっきりの想定外だったのだ。
「それはこれから検討しよう」
そこで柳が口を噤んだ。
テーブルに両肘をついてから合わせた両手を鼻先に当てて、小此木を見据える。
「……取り分は?」
「純利益の30%でいいよ」
「無償じゃねえの!?」
赤村が驚愕の声を上げたが、残念ながら無償のわけがなかった。それに、もしも小此木が隊長の心意気に感動して「はいどうぞ」と三〇〇万を提供するような人間だったら、柳もこの話に乗ろうとは思わなかっただろう。
見返りを求めないような人間は、この中学校では決して信用されない。
「それはまた寛大なことだ。────妙ちゃん」
柳がいつものように状況を噛み砕いて補足した。
「小此木くんの融資があればプール金を解体できる。もちろんこれは洗練されたやり方ではないし、倫理的に正しいとも言い難い。僕らの大義名分もなくなって彼らと同じ立場にまで落ちるけれど、妙ちゃんの目的は果たせるはずだ。実利を取るか、大義を取るかは妙ちゃんにお任せするよ」
柳は客観的な立場で物事を見極め、できるだけ多種多様な選択肢を────例えその選択肢が更なる困難を招くとしても────用意するためにここにいるのだ。
隊長は柳の話にじっと耳を傾けていた。長い睫毛を何度か揺らして瞬きし、そしてこれまでの暗い空気を吹き飛ばすように凛とした声で結論を述べた。
「わたし達は道徳家じゃない。以上」
隊長が立ち上がった。
「────それではこれから、プール金鹵獲のための会議に移ります」
大きな模造紙をコルクボードに貼り付けて、手を使ってばしっと伸ばした。
「────これから各班に分かれて動く事とします。二週間後の会議前日に各班の成果を発表し、小此木くんが出資できると思ったら、そしてわたしが勝てると思ったら、正々堂々戦いましょう。まずは浦原くん」
「おうよ」
隊長がサインペンで可愛い文字で戦術立案班と書き殴った。
「市内対抗戦では納涼お月見杯のようなデータ戦術が使えないと思う。だから全く見知らぬプレイヤーと戦う戦術を立案してください」
少しだけ考える。
今回は事前にハンドヒストリー収集ができないから、ブラインドの低いうちに情報収集をせざるを得ない。古き良きタイトアグレッシヴの再来だ。著名なチェスプレイヤーが言うように、序盤は本のように、中盤は奇術師のように、終盤は機械のように、戦う事が求められるはずだ。
「敵プレイヤーは当然連携してくると思うが、それも込みで立案するか?」
「その辺りはやなぎんに対処してもらう。少なくとも普通のポーカーがプレイできるレベルまで復旧させるから、その前提で動いて」
「よしきた、任せてくれ」
「ちなみにわたしも加わるのでどうぞよろしく」
隊長は戦術立案班の下に「わたし&浦原くん」と書きながら、
「やなぎん。今、言ったように、市内対抗戦では他校の生徒が連携する等への対策が必須になると思う。ポーカートーナメントだけじゃなくて広域的な対策もね。様々なケースが想定されるので、それを全部シナリオ別に列挙して対策に取り組んで」
隊長は柳にできるかどうか? などという問いは投げ掛けなかった。
「分かった」
サインペンの黒インクが景気の良い音を立てながら、シナリオ別対策班の下に「やなぎん」という文字に化けていく。
「さらに必要なのが敵プレイヤーの情報収集。これは何もポーカー技術についてだけじゃないよ。敵プレイヤーの個人的な背景、学校毎の諸事情について徹底的に洗って各班に情報を流して欲しいの。他校の取材に赴く必要があるので新聞部にお願いしようと思っているんだけど、赤村くんにも入ってもらいたいな」
「俺ですか。あまりお役に立てないように思えますが」
「ううん。会話による情報収集が主軸になるし、記憶力のいい赤村くんは絶対に役に立ってくれると思う。すぐに新聞部への入部届を書いておいてね」
「えっ!? 俺、新聞部に入るんですか?」
「うん」
確かに、新聞部の部員証があった方が他校の取材も円滑に進められるだろう。
新聞部に入部する事になるなど一分前には考えてもいなかったであろう赤村は驚いていたが、隊長は決定事項であると念を押して情報収集班に「新聞部(赤村くん入部)」と書いた。
「しかし、第二回会議では俺も顔合わせをするんですよね? その時にスパイ活動が露呈するのはあまりよろしくないかと」
なおも食い下がる赤村に隊長が微笑みかける。
「第二回会議の前に髪の毛切っちゃおうよ。坊主も似合うと思うよ」
その一言で赤村が硬直した。
「ねえねえ、ぼくは? ぼくも秘密任務とかやりたいんだけど」
小此木が無邪気に手を挙げた。
「小此木くんには一番重要な仕事をお願いしたいの。必要があれば最優先で人を宛てがうつもり」
「なになに?」
隊長はでっかい丸を書いて、その中に「三〇〇万円!」と書いた。
「────資金調達」
小此木はぽんと手を打って、
「はいはいはいはいそうだねえ。どうやって国内に資金持ってくるか考えなくちゃなあ」
既にノートパソコンを開いてポーカー審議会の特別会議日程を調整していた柳が手を挙げた。
「資金持ち込みに関してはいくつか考えがある。法的な観点からも助言できるはずだ」
こうして資金調達班「小此木くん&やなぎん」が三〇〇万を調達する事となった。
そしてこの場の空気にすっかり気圧されてしまった榊原と木佐の方を向いた隊長が、落ち着き払ったような仕草で微笑んでみせた。
「榊原くん。それと木佐さんには柳くんの補佐をして欲しいの。シナリオ別対処や風評被害対策にはポーカー審議会や渉外連絡会の交渉が不可欠だと思うんだ」
「その前に一応聞いておくが、」
「何でしょう、榊原くん」
椅子にどっかりと座った榊原が目を細めて、ポーカーモンスターズの五人を順繰りに見ていった。
「……この話に乗る事で、当然俺達にも旨みはあるんだろうな? ポーカー審議会や新聞部を動かすには、それなりの材料が必要だぞ」
「少なくとも、王座の不在は避けられます。それ以上の事を今は確約できないけれど、榊原くんや木佐さんの立場は分かっているつもり」
しばし考え込んでいた榊原は、この状況下で反対して決別するよりも賛成する事に多くのメリットを見出したのか、素っ気なく頷いた。
「それじゃあ、奴らには東本郷中学校らしい戦い方を見せてやろう」
「東本郷中学校らしいってどんな?」
赤村が首を傾げてそう尋ね、榊原がいつものように自信満々な態度で答えた。
「事前の根回しとごり押し外交」
狭い部屋に七人もの人間がいるからか、何だかさっきから身体が熱くなってきた。
────勝てるかどうかはまだ未知数だ。
これからの二週間でどれだけ精度の高い作戦が出来上がるかに懸かっているが、自分のやる事は決まっている。さしあたってはポーカーの戦術について、戦闘狂の隊長と徹底的に討論しなくてはならないだろう。しかし、面白くなってきた事は否定できない。
いつものように話を総括しようと柳が立ち上がった。
「もう一度確認しておく。タイムリミットは二週間後の金曜日までだ。クリスマス・イヴに行われる第二回会議までに各班が成果を発表する。小此木くんと妙ちゃんが総合的に判断し、いけると思ったら三〇〇万円の全額勝負だ」
異論がない事を確認してから柳が両手を合わせてぱちんと鳴らした。
「では仕事に取り掛かろう」
怪物たちのチームプレーは
悪だくみで本領を発揮する。
次回、血湧き肉躍る第二回会議、開幕!
12/19(月)更新予定!
